7月26日(土)、札幌市資料館SIAFプロジェクトルームにて今年度1回目の教育喫茶を実施しました。
教育喫茶は、教育に関わる先生や学生、アーティストなどが集い、教育とアートに関する課題や可能性を話し合うコミュニティの場として2023年にスタートし、以来2か月に1回のペースで続けてきました。
今年度最初の開催となる今回は、SIAF2027に向けた教育喫茶のキックオフとして、「SIAF2027『PLANET SNOW』から考える、これからの教育」をテーマに、店長(講師)の先生方から事例をご紹介いただきながら意見交換を行いました。
天気はあいにくの雨模様でしたが、会場とオンライン合わせて7名にご参加いただき、雨雲を吹き飛ばすような熱い議論が交わされました。

テーマ「SIAF2027『PLANET SNOW』から考える、これからの教育」
―STEAMでひらく、創造的なまなびの可能性―
―鑑賞からひらく、対話と気づきの教育―
6月に発表されたSIAF2027のテーマ「PLANET SNOW(プラネット・スノー)upas mintar ウパシ ミンタラ / upas nociw ウパシ ノチウ」。これには、札幌をひとつの星に見立て、そこに暮らす人々の暮らしや歴史や文化など、その星に広がりうる世界をみんなで考え、未来を探求していこうという想いがあります。
それでは、そんな「PLANET SNOW」にはどんな学校・教育があるのでしょうか?
こんなワクワクするような問いを入口に、今回はそういった未来の視点から、学校教育の可能性についてじっくりと考えていきました。
今回店長(講師)を務めてくださったのは、STEAM*教育やアートを活用したユニークな学びに取り組まれている佐藤 祈先生(南幌町立南幌中学校)と中里彰吾先生(札幌市立中央小学校)です。
*STEAM…科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術・リベラルアーツ(Arts)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。教科を横断する学びの手法として注目されています。
お二人の先生から、普段の授業で取り組んでいる事例をご紹介いただき、その後は参加者との意見交換を中心に進行しました。
「鑑賞からひらく、対話と気づきの教育」
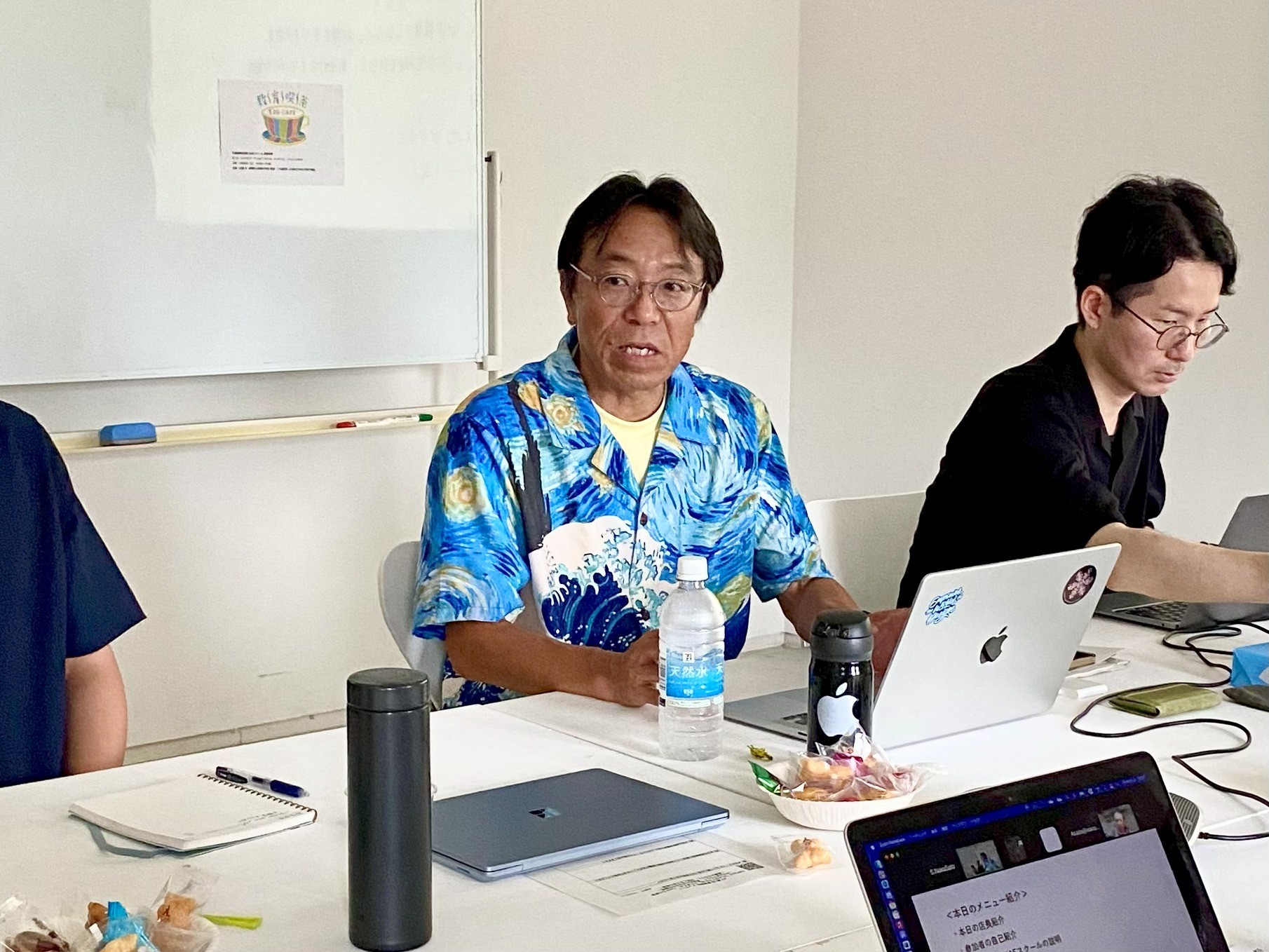
まずは、中学校で美術と技術の授業を担当されている佐藤 祈先生(写真中央)より、STEAM教育の概略と、アートの力を活かした学びの可能性についてお話を伺いました。
STEAM教育は元々、科学技術分野の人材を育てる「STEM」として提唱されていましたが、近年は、新しいものを生み出す“イノベーション”には、芸術的な発想や創造性が不可欠だという認識が広まり、芸術(Arts)が加わって「STEAM」という形に進化しました。
ただ、実際の教育現場では、まだまだ芸術の要素が十分に活かされていないと感じているとのこと。そんな中で、佐藤先生が美術の授業で実践している取り組みについていくつかご紹介いただきました。
タブレットを使って美術の教科書に載っている好きな作品の写真を撮り、なぜその作品を選んだのかをコメントと一緒に生徒同士で見せ合う交流会を開いたことなど、ここでは全てお伝えしきれないくらいたくさんの事例が!
取り組みの中で佐藤先生が特に大切にしているのは、気に入った作品や自分の作った作品に、込めた思いやストーリーを記載したキャプションを添えることだそうです。生徒たちが作った作品は、制作過程を写真で記録し、作者の思いが詰まったキャプションと一緒に展示することで、鑑賞する側もより深く作品を味わえる工夫をしているのだとか。
自分の感じたことを言葉にして、それを他者と共有する。アートを通して対話を図ることの重要性が、とても力強く語られました。

また、佐藤先生は技術の授業でも、グループワークを取り入れることで、プログラミング的な思考だけでなく、仲間とのコミュニケーション能力も育むことを目指しているのだとお話しされていました。
個人作業で完結しがちな美術や技術の授業を、グループワークや対話を取り入れることで、他者との交流や考えの交換が生まれる場へと変えていく。佐藤先生のお話からは、そんな未来の授業へのヒントが感じられました。
参加者とのディスカッションでは、さらに話が広がります。
参加されていた支援学校の先生からは、自身の教育現場では子どもたちの体を動かす表現活動や抽象的な表現がとても大切にされているため、こういった美術や技術の授業はとても相性が良いという感想がありました。
さらにそこから、デジタル技術を活用することで、これまで創造的な活動に参加することが難しかった子どもたちも、自分の力を発揮できる可能性が広がるといった意見もありました。

他の先生からもデジタル技術の最新事例についてご紹介いただきました。
AIを活用すると、3Dモデリングのような複雑な作業も、言葉で指示するだけで簡単にできるようになるとのことです(!)
専門的な技術がなくても、AIの力を借りれば誰もが自分のアイデアを自由に形にできる時代が来るかもしれません。そうなれば、子どもたちの豊かな発想や創造性を、もっともっと引き出すことができるのではないか?そんな議論が白熱し、会場は更なる熱気に包まれました。
「STEAMでひらく、創造的なまなびの可能性」

佐藤先生に続いてお話しいただいたのは、学校でテクノロジーを活用したSTEAM教育に取り組んでいる中里彰吾先生(写真右)です。
中里先生は、テクノロジーをより良く使いこなすためには、その仕組みを理解することが大切だとお話されました。
単にツールを操作できるだけでなく、その背後にある原理や仕組みを理解することで、より深く、そして創造的にテクノロジーを活用できる子どもを育てるという考え方です。
そして具体的な取り組みとして、「テレビはどうやって画面が映るのか?」「コンビニの入店音はどうやって鳴るのか?」といった身近な疑問を、実際にプログラミングで仕組みを再現することで解消し、テクノロジーを操る楽しさを体験しようという先生の実践例が紹介されました。
現代の子どもたちは、生まれたときからデジタルツールに囲まれて育っているからこそ、単に与えられたものを使うだけでなく、「自ら考え、創造する力」がより強く求められます。
中里先生からは、AIに何でも任せるのではなく、「ここまではAIに手伝ってもらうけれど、ここからは自分で考える」という、自立心を育む教育がこれからの時代には欠かせないとのお話でした。
AIがスライドを独自に解説する一幕もあり、会場からは驚きの声が。
ディスカッションの中で挙げられたのは、先生方もAIを活用すれば、資料作成の効率を上げたり、授業準備の時間を短縮することができ、そうして生まれた「ゆとり」の時間を、子どもたちと向き合い、より創造的な教育活動に充てることができる可能性です。
一方で、学校現場では、現状まだまだテクノロジーの活用に温度差があるそうです。
また、中には子どもたちの方が大人よりもテクノロジーを使いこなしており、かえって大人がその本質を誤解しているという一面も。
日々進化していく新しい技術を、ただ昔ながらの授業に当てはめるのではなく、先生方が課題意識を持ち、日々進化していくテクノロジーを柔軟な発想で受け止めることが大切だとお話されていました。
「教育喫茶での取り組みがもっと広がり、繋がりのある方が増えていけばいい」(中里先生)、「テクノロジーが進歩していく中でも、ものづくりの理念は忘れたくない」(佐藤先生)というご両名の熱いコメントで、ディスカッションは締めくくられました。

参加してくださった方からは、
・STEAM教育の必然性を改めて強く感じました。
・自分の実践に対して、改めて色々学ぶ機会となりました。
・ICTを活用することで生徒の興味や関心を引き出すことに成功しているのは、参考になる。
など、様々なご感想をいただきました。(アンケート一部抜粋)
今後の教育喫茶では、引き続き参加者と意見を交わしつつ、アートとテクノロジーの可能性を探りながら、新たな学びのかたちについて模索し、SIAFスクールの出前授業などでの活用も視野に入れていきます。次回は9月に開催予定です。詳細は決定次第こちらでお知らせします。
今回ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!
「教育喫茶」では、教育に関わる先生や学生、アーティストなどが集い、色々なテーマに基づいた、実験的なプログラムを作ったり、体験したりする中で、学校と芸術祭が「これからの教育」を共に考え創造するプラットフォームとなることを目指しています。
興味のある方、参加希望の方は事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ先:operation@siaf.jp